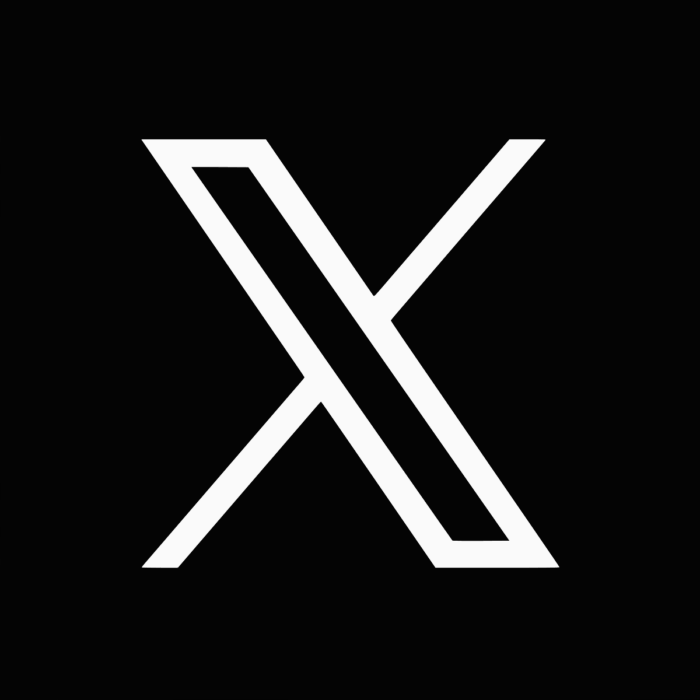(ネタバレを含みますのでお気をつけください。)
英国ダガー賞を日本人で初受賞というニュースをきっかけに読んだ。作者の王谷晶さんのお名前も知らず、名前の読み方や性別も知らなかった。とはいえ、名前の読み方や性別がわかったからなんだというのか。
書評とネタバレについて、そもそもここに文章を書き連ねる理由まであれこれ考えさせられた。書評は作品のあらすじを書くに留めるべきか。この書評の読み手に作品を薦めるためなら、興味をそそる導入であるべきだ。だが、自分が読んで感じたことを言語化するための自分向けWebログの性格が強いと、ネタバレも含めて書き記したい。というか、書かざるを得ない。とはいえ、ミステリー小説の書評でいきなり犯人を示す愚はさすがに避けたい。そんな葛藤があるんだなと再認識した。ここまでの内容だけでも「ネタバレに気をつけるべき仕掛けがある」というネタバレを含んでいる。その伏線や読書体験が鮮やかだっただけに、これからの読者の体験を損なうことだけは気をつけたい。改めて書評の目的というか姿勢を整理すると、自分が読んだもの、感じたことをネタバレを気にせず書く。私が感じたことを既読者の方々と共有することで、その読者に共感や違和感という読後体験の奥行きが生まれれば幸いだ。
多勢のヤクザにも怯まないほど喧嘩の強い女・新道依子が、暴力団・内樹會の会長の一人娘・内樹尚子の護衛にスカウトされる。大学に通う尚子は、ひとり親の会長から生活全般を制限・監視され、学校以外の時間、服装に至るまで自由がない。尚子の母親は会長の部下だった「長ドスのマサ」と不倫の末に逃走中。依子と尚子のエピソードと並行して、芳子と正という二人暮らしの生活も語られる。共に白髪の二人は偶然、自動車事故の現場に遭遇、負傷者を救出したのち野次馬のカメラを避けるように逃げる。世間から距離を置く様子に、二人のただならぬ事情がうかがえる。芳子と正は、日本のどこかに逃走した尚子の母親とマサと思われる。依子と尚子は次第にお互いの状況や出生を理解し打ち解けていくが、尚子の母とマサの居場所が見つかったと一報が入り、会長は急ぎ刺客を送る。逃げる支度をする芳子と正の家に追手が迫る。芳子は必死に刺客と争うが、あれ?めっぽう強い。さすが会長の妻だから強いのかな?と思ったら、明かされる事実。芳子は40年後の新藤依子の姿だった!つまり、依子と尚子、芳子と正の2つのエピソードは場所=空間が異なった別人物ではなく、時間が異なった同一人物だった。内樹會から逃げた依子と尚子が、40年を経て芳子と正になっていった。尚子の読みは「なおこ」ではなく「しょうこ」だった。まるで同時進行のように語られていた芳子と正は、長ドスの「マサ」ではなく「しょう」だった。この名前の読み方を使った叙述トリックに気持ちよく足をすくわれた。
感心しながらも、さらに興味を覚えるのは英国ダガー賞だ。漢字の読み方を含むトリックに、どのように英語で応えたのか。また、オーディブルのような朗読メディアの場合、このレトリックは成立するのか?アクション映画のような本作、映像化も面白そうだが果たして可能か?などなど、叙述トリックから派生する様々な問題や疑問が頭をよぎるのも楽しい。
ババヤガとはスラブ民話での魔女のことらしい。明確には語られないが、暴力に異様に惹かれる依子という女が、鬼婆のような人外へ覚醒する物語とも解釈できる(依子というキャラクターは暴力シーンにこだわる作者の投影とも読める)。さらに、男女、夫婦、親子、兄弟姉妹といった名前のある関係性とは異なり、依子と尚子の女二人の40年の生活・関係に付ける名前はなく、もはや性別も名前すらも曖昧だ。愛ではないが深い絆を持ち、お互いを最も大事に考えている。ただ、「誰かの何かとして」はもう生きられない二人は、今の世間では生きづらい。そのカテゴリ外に居ることが、異端の者という意味での魔女・鬼婆であり、二人でそうなるために生まれてきたのだとも悟る。夜にこそババヤガは輝くのか、明けるべき夜もあるのだろう。