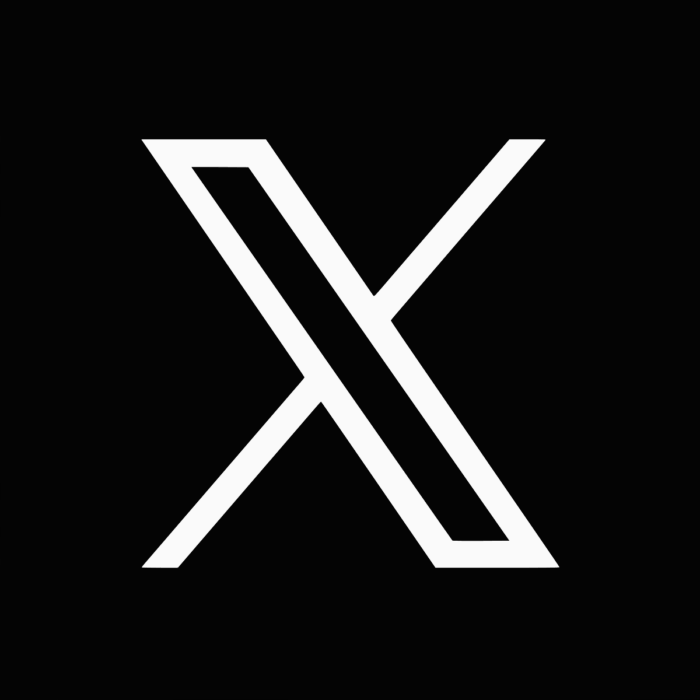15世紀前期のP王国というヨーロッパ風の国。架空の宗教C教が権威を持ち、宇宙の中心が地球である天動説を公認の学説とする。神の力を示す天動説に対して地動説は異端の教え。秩序を乱すものは処罰の対象であり、異端者はときに極刑にもなる。天文学の研究に高いリスクが伴うという舞台設定だが、史実では地動説を語るだけで火刑までにはならなかったようだ(地動説を含む異端を唱えて火刑になった人はいる)。だが、この極端な設定により、新たな知識を信じることに命をかける、そんな狂気が描きやすくなる。
地動説を信じる登場人物が放った「不正解は無意味を意味しない」という言葉が印象に残る。少し回りくどいが、不正解にも意味がある、と。それは、ある人の行動が正解か不正解かよりも、問うことそのものに意味がある、と捉えられる。『私の行動は誤りかもしれないが、この問いは新たな知性に貢献している』という確信がそこにある。積み重なってきた多くの問いの先に新たな知性が生まれる。イマココにあるあらゆる考えは先人の問いの積み上げであり、命の集積の結果ともいえる。そんな「思いのバトンリレー」が本作で鮮やかに描かれる。バトンは、夜更けから深夜、夜明け、朝焼けとまるで地球の運動のように巡る。
そのような知性が伝播するための装置として、文字や本という媒体も本作の大事なテーマだ。手書きのノートや本に加え、紙以外の媒体や活版印刷も登場し、地動説の研究が人から人へ伝わる。本を通して私たちは千年前の作者とも出会い、語り合い、友人になることもできる。当たり前のように思えるが、よく考えれば驚くべきことだ。そして、ある思想が社会に浸透し変化をもたらすには幾世代もの時間がかかる一方で、人の寿命はあまりにも短い。その隔たりをつなぎとめてくれるのが、まさに書物であり文字なのだ。文字を通して人は永遠の存在にもなれる。
地動説の確立を通して、あるアイデアや考えがどのように人々に伝播していったのか、それは例えばこんな物語だったかもしれない。本作はわずかなフィクションを交えつつ、人の思いの力強さを示す。「地球(を守る)」という言葉に「かんどう」というルビを振るシーンもあった。タイトルの「地球の運動」とは、文字通りの天体運動と同時に、この世の美しさに感動し世の中を突き動かす人々のことだ。
感想はぜひ
Xのツイートへの返信
でお聞かせください。
更新情報をXで発信中。フォローしていただければ励みになります。