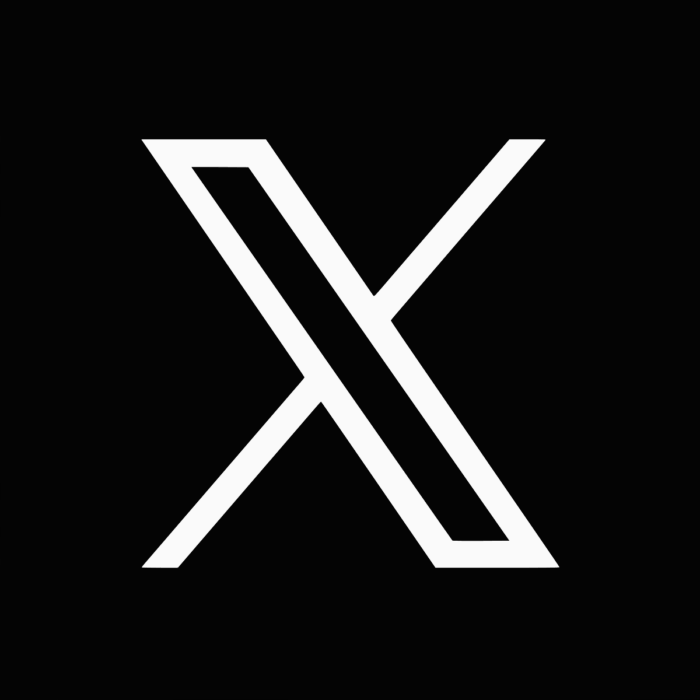薄暗い夜の街、路上販売や駅の雑踏、インド・ムンバイで暮らす人々のナレーションから始まる。電車で通勤するプラバはムンバイの病院に勤める看護師。仕事でドイツに行った夫から1年以上連絡がない。同居中のアヌは職場の後輩。アヌはヒンドゥー教徒だが、ムスリムの彼氏がいて職場で噂になっている。病院の食堂で働くパルヴァティは夫を亡くして久しい。しかし、長年住む家の居住証明書類に夫の名義しか無く、高層マンション建設のため立ち退きを迫られている。
プラバ、アヌ、パルヴァティと、3人の女性はそのままならなさに戸惑い、虚空や彼方を見つめる。何かがおかしい。なぜドイツに居る夫は電話すらしてこないのか?なぜ異教徒との恋愛はダメで親はお見合いを勧めるのか?なぜ名義が亡き夫だからといって住居から妻が追い出されるのか?大声をあげず、静かな沈黙で訴える。雨の多いムンバイの夜、部屋の窓からプラバが見つめる先には高層マンションやスラムの家々の街明かり。こちらの部屋にはない家族の生活が、遠く彼方の光にはあるのか。こちらが暗いほど、遠くの理想は輝いて見える。
パルヴァティはムンバイの家を引き払い、海が近い郊外の実家に引越す。プラバ、アヌも共に荷物を運び、日差しが溢れるバスで移動する。都会の夜のネオンと、郊外の昼の自然光が対照的だ。この郊外で、プラバはまるで口寄せのような夢か現実かわからない奇妙な体験を通して夫からの決別を果たす。目覚めたようなプラバは柔らかな微笑みで「彼を呼んで」とアヌに伝える。おとぎ話のお菓子の家のようなカラフルな電飾のほったて小屋で4人が出会う。その出会いと優しい会話を包むように星空が浮かぶ。それぞれの抑圧を脱したというよりも手を取り合ってそれを受け止めている。彼女ら自身がこれからを照らすひとつの希望の光となったのだ。後ろで踊る若い店員は、それを祝福する天使のようだ。