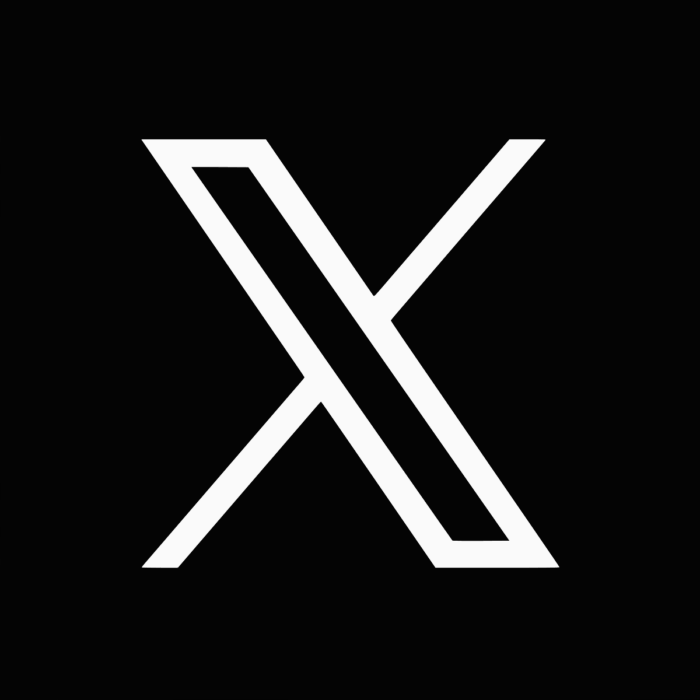原題と邦題が違う例は映画でも本でもよくある。サンデルといえば『これからの正義の話をしよう』がベストセラーになったこともあり、邦題にあえて「正義」という言葉を足したのか。原題は The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good 。直訳すると「功績主義の圧制――共通善はどうなってしまったのか」といった感じだ。Merit=功績。Meritocracy=功績主義。ただ、日本語では「能力主義」とも言われる。本書の内容からすれば「功績主義」が一番近いが、日本での文脈を考えると「能力主義」としたほうが通じやすい部分もある。どちらにせよ邦題はだいぶ意訳になっている。
出版は2020年9月。トランプ政権(2017〜2021)の末期で、トランプとバイデンの大統領選挙の直前だ。サンデルはポピュリズムの原因としてメリトクラシーを挙げる。もちろんブレグジットなど欧州の事例にも触れるが、中心はあくまでアメリカ政治、とりわけオバマ政権下の民主党の政策を批判している。
功績主義は「努力すれば成功できる。できないのは自己責任」という考えを押し出す。そのため大学学位の取得が強調される。結果として学位を得たエリートは「自分の努力の成果だ」と思い上がり、学位を持たない労働者は尊厳を失う。グローバル化のしわ寄せやアファーマティブアクションも絡み、白人中産階級が「自分たちは軽んじられている」と感じるようになる。この相互の反発が分断を深め、トランプ政権を生んだ。教育制度のあり方も批判されている。本来なら社会の流動性を高めるはずの大学が、むしろ階層の固定化に加担しているというのだ。SATのような試験は準備にお金をかけられるかどうかで結果が左右され、家庭の経済状況が学力評価に直結する。努力以前に「運」の要素が大きい。
ではどうすればいいか。サンデルは、一つの案として「入試をくじ引きにする」という大胆な仕組みを提示する。もちろん一定の学力ラインは必要だが、その上で選抜をランダムにすれば経済格差の影響を和らげられる。他にもコミュニティカレッジや職業訓練校の強化など、労働の尊厳を回復する方策が語られる。
トランプ政権に対しては批判的なメディア報道が多かった。建設的な批判というより、時に嘲笑に近いトーンもあった。ただ「なぜ彼が当選したのか」をきちんと理解する機会は少なかったように思う。本書を読むと、例えば政権がハーバード大学への助成金を止めようとした背景も見えてくる。メディアの評価もまた、学位を持つエリート層のフィルターを通したものだった可能性は否定できない。