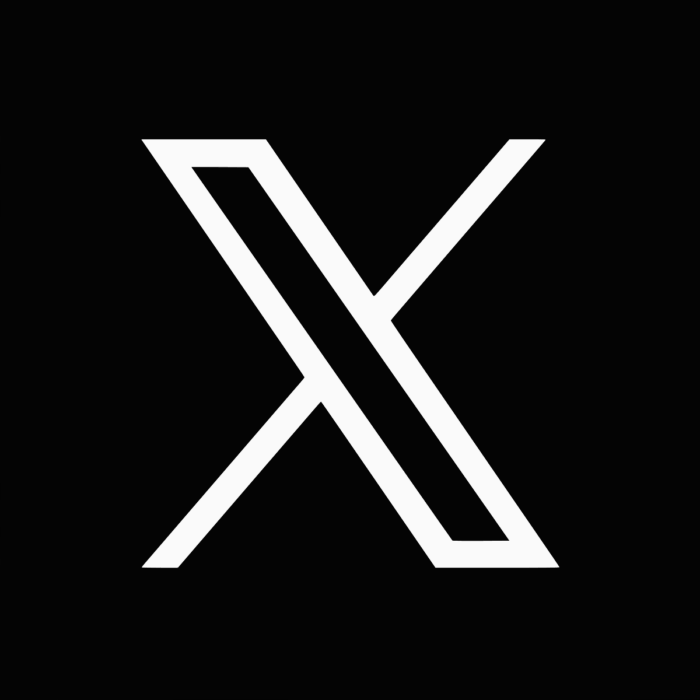海外で翻訳版が評価され、改めて日本でも評判となった本作を電子書籍で読んだ。作者が着想を得たといわれる実際の事件「首都圏連続不審死事件」は2007〜2009年に起き、報道や裁判が世間を騒がせたのは2010年代前半頃。本小説の初版は2017年、翻訳版の出版は2024年であり、意外と時間が経っていたのだと読後に知った。また、元の事件について記憶があまりなかったため、どこまでが事実に基づいているのかはわからず、むしろ前提知識や先入観なしで読むことができた(と思う)。
週刊誌記者の町田里佳は、都内の連続不審死事件の容疑者として収監中の梶井真奈子から取材の了承を得る。事件の聴取には誰が相手でも応じなかった梶井だが、料理や美食の話題を切り口にすることで面会にこぎつけた。料理好きで里佳の親友でもある伶子の助言がきっかけだった。東京拘置所での面会を通じて、里佳は梶井に勧められた食材やレストランのメニューをひとつずつ味わっていく。梶井の食べてきたものを追体験しながら、事件に関与した彼女の思考を探ろうとするのだ。しかし、食欲に正直な梶井の姿勢は、女性の社会的な抑圧から解き放たれているようで、里佳は少しずつ彼女に惹かれはじめる。やがて食にとどまらず私生活まで翻弄され、伶子や関係者を巻き込みながら物語は展開していく。
取材が進むにつれ、里佳・梶井・伶子の三人の生い立ちにも触れられ、それぞれが抱える事情から女性のさまざまな抑圧が浮かび上がる。事件における悪女像、食に起因する体型や料理などのケア、結婚や家族の在り方など多岐にわたる。そうしたフェミニズムの課題を具体例として提示しつつ、三人の間では惹かれあい、憎みあう感情が揺れ動く。その心の変化が静かにでも確実に、ふとした言葉やほんの小さな揺らぎとして描かれる点が印象的である。
さらに、味だけでなく匂いや環境音など五感を駆使した臨場感ある食レポや調理描写は、読んでいるとお腹が減ってくる。実在の商品や食材、飲食店も登場するため、同じ料理を通じて小説を追体験できる楽しみもある。個人的にはまずエシレのバターしょうゆご飯を試してみたいと思った。梶井が勧める多くの料理にはたっぷりのバターが欠かせない。タイトルでもあるそのバターは、本来なら控えるべき存在であり、抑圧された女性の食欲=欲望を象徴する。一方で、その抑圧をはねのけ、明日の活力となる凝縮された力の源でもある。
感想はぜひ
Xのツイートへの返信
でお聞かせください。
更新情報をXで発信中。フォローしていただければ励みになります。